(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)
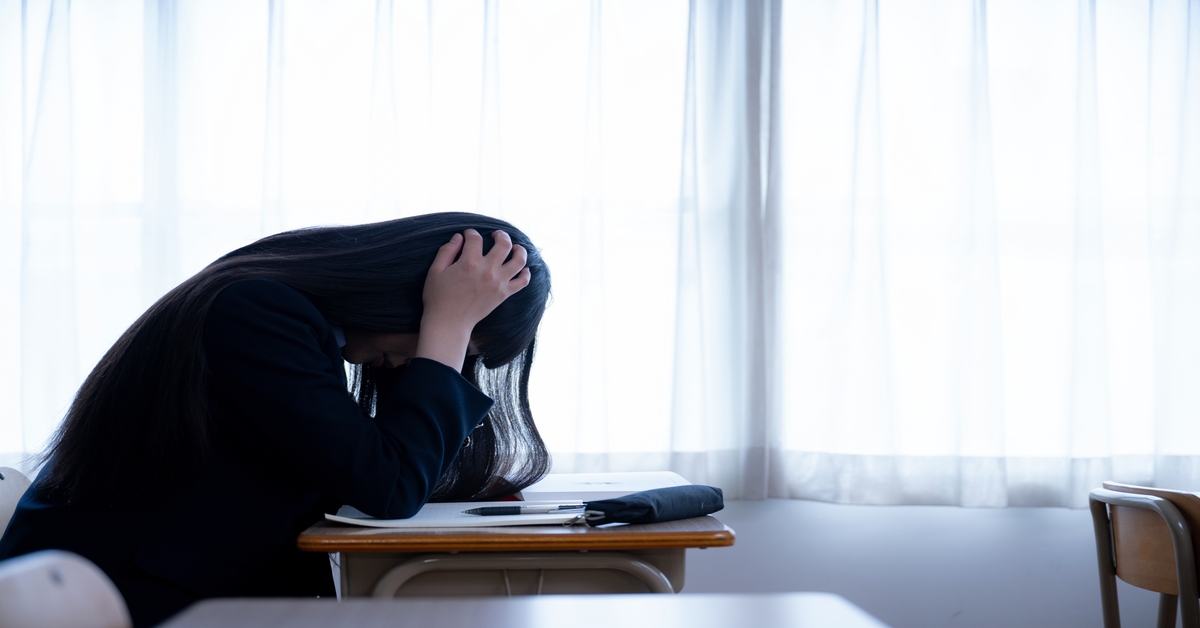
生活保護は年齢に関係なく誰でも利用できるセーフティーネットです。
しかし、生活保護を若者が利用するのはずるいと考える方が少なくありません。
その背景には、若者なら働けばいいなど、色々な誤解も浮き彫りになっています。
本記事では、生活保護を若者が利用するのはずるいのかを中心に、若者を取り巻く生活保護の現状や理由を解説します。



最初に、どれだけの若者が生活保護を利用しているのかについて解説します。
厚生労働省の調査によると、生活保護を受け取っている10代・20代は全体の13%程度です。
そのうち、19歳以下がおよそ10%ほど、20代が3%ほどとなっています。
参照:厚生労働省
19歳以下は2011年・2012年をピークに下がっており、20代は長らく横ばいの状況です。
一方で、65歳以上が全体の半数以上を占めるなど、生活保護を受け取る人たちの高齢化が加速していると言えます。
貧困状態にある18歳未満の子どもについて、子どもの相対的貧困率が2021年で11.5%あります。参照:朝日新聞
生活保護を受け取る若者と比較すると、その数値はほとんど変わりません。
現状では子どもの相対的貧困率に改善が見られますが、ようやくOECDの平均値を下回った状態です。
子どもの貧困問題は問題視され、各地でこども食堂が誕生するなど、生活保護との関連もありそうです。
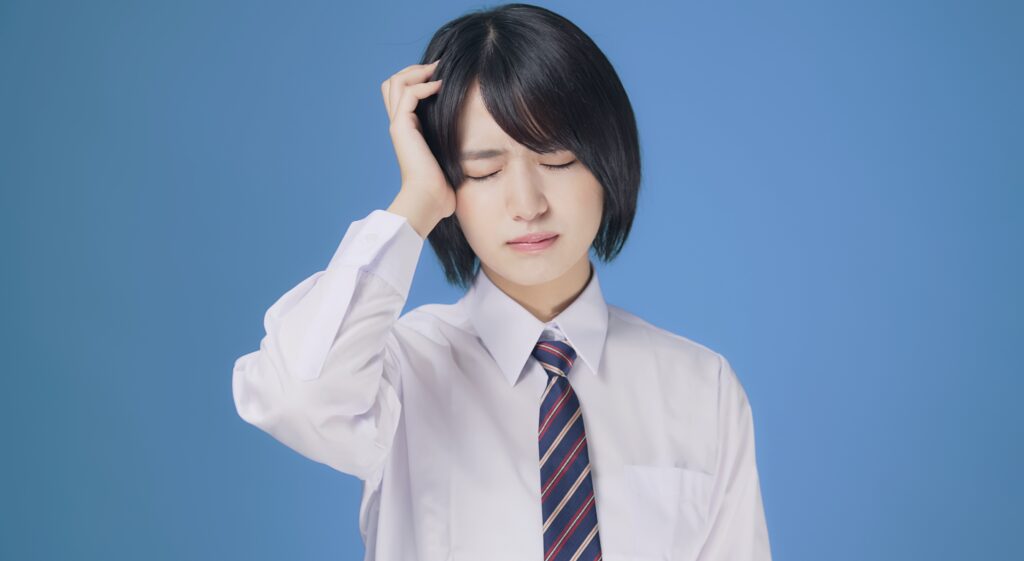
そもそもなぜ生活保護を若者が利用するのはずるいと感じるのか、そこにはいくつかの理由が挙げられます。
上記の理由について詳しく解説します。
生活保護を受け取る若者がずるいと感じるのは、働かずにお金をもらっている点が考えられます。
若いから働けるはずなのに、働こうとしないのは怠けていると感じ、ずるいと感じる人が少なくありません。
一方で、若者の中には肉体的・精神的な病気のため、働きたくても働けない人がいるほか、障害を抱えて生活保護に頼らざるを得ない人もいます。
精神的な病気で働けず、生活保護を受け取っていた場合、外から見てもその様子はわかりにくいため、「怠けて生活保護を受け取っている」ような誤解が生じやすいと言えるでしょう。
生活保護を受け取っている方が裕福な暮らしができるのではないかと感じている人も中にはいます。
生活保護費は基本的に非課税のため、手取りで丸々もらえることから、地域や世帯人数によっては年収200万円以上に換算する生活保護費を受け取れます。
一生懸命働いて同じ程度の年収の人からすれば、生活保護をもらった方がいいのではないかと感じる人が出てきても不思議ではありません。
一方、最低生活費に届かない収入しかなければ、差額分を生活保護として受け取ることも可能です。
つまり、働いている人でも生活保護は受け取れます。
生活保護に対する誤解が、ずるいと思わせる要因になっている可能性が高いです。

10代や20代の若者も受給している生活保護ですが、受給できる条件としてどのようなものがあるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
本項目では、若者が生活保護を受給できる条件についてまとめました。
結論から言いますと、若者も高齢者も、生活保護を受給できる条件は同じです。
生活保護を受給できる条件は以下の通りです。
若者だからといって厳しい基準が設けられていることはなく、上記の条件を満たせば生活保護の受給は可能です。
例えば、病気やケガで働けず、周囲に親族がいない若者は生活保護を受給し、働けるようになるまで休養をとることができます。

体力もあってバリバリ働けるはずの若者が、生活保護を利用せざるを得ない理由として以下のことが挙げられます。
本項目では、若者が生活保護を頼る主な理由についてまとめました。
近年、精神疾患を抱える若者が増えており、上場企業を対象にした調査で「心の病」を抱える20代以下の若者は43.9%と20年で3倍以上となっています。参照:公益財団法人日本生産性本部
若者以外の年代は20年前と比べて心の病を抱える人の割合を減らす中、若者だけ大きく増えている状況です。
精神疾患となり、働きたくても働けない若者が結果的に生活保護を受給することになったと考えられます。
2023年に発表された調査によると、15歳から39歳までの引きこもりの割合は2.05%で、2016年時と比べて0.5%ほど増えています。参照:NHK
コロナ禍の影響が大きいとされ、居場所をリアルな空間ではなく、インターネットなどのバーチャル空間で見つけようとする動きが見られます状況です。
一方、誰にも相談したくないと答える人は15歳から39歳の引きこもりの方の中で23%程度と高めです。
そのため、引きこもりの子どもを抱える親が、子どもに一人暮らしをさせて、生活保護を受けさせるケースもあります。
親族のほか、知人・友人など周囲に頼れる人がいない人も生活保護に頼らざるを得なくなります。
特に親族との関係が悪く、過去に虐待やDVなどを受けていた人などは、居場所を知られたくないなどの理由で親族に頼りたくないと考えるでしょう。
また、親族も貧困で、頼りたくても経済的に頼れないケースもあります。

生活保護は誰でも利用できるほか、自立を促す仕組みもあるため、生活保護を利用した若者の中には脱却したケースもあります。
最後に、実際に生活保護を利用した若者の事例をご紹介します。
20代に精神的な病気を理由に生活保護を受け取った若者は、数年ほど生活保護に頼った後、生活保護から脱却に成功しています。
きっかけは数年前から日本でも盛んになったUberEatsの存在で、何かのためにと貯めていた生活保護費から自転車を購入し、配達員となりました。
そこでしっかりと稼げるため、生活保護からの脱却を目指して活動を重ねていき、ついに生活保護の脱却に至りました。参照:読売新聞
精神的な病気などもあり、一時的に無気力の期間があっても、何かをきっかけに仕事に目覚め、生活保護の脱却までに至るケースも十分にあります。
生活保護を受け取っていた人が実際に自立するケースはあまり高くないのが現状です。
読売新聞の調査では、2020年度に就労支援を受けた生活保護受給者のうち、41.1%の人しか実際に就労できなかったことが明らかとなっています。参照:読売新聞
そして、実際に脱却できた人はわずか5%ほどと、自立するのはかなり大変と言えます。
背景には病気を抱えながら就労する難しさなどがあり、なかなか就労までたどり着くのが難しい状況にあります。
若者の場合、回復さえすれば自立はしやすいものの、本人の努力と自治体の支援などがなければ成立しにくいと言えるでしょう。
この記事もおすすめ


生活保護を若者が利用するのはずるいと考えるのは、ネットだけの声ではなく、自らも貧困にあえいでいた若者が感じていることもあります。
身内に生活保護を受け取っている人がいて、その人の姿を見て生活保護を利用しないでおきたいと考えるケースもあるのです。
とはいえ、生活保護は国民1人1人に与えられたセーフティーネットであり、たとえ若者でも、生活が苦しい場合には積極的に利用しても全く問題はありません。
当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!
審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
当社のおすすめ新着物件はこちら!


