(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)

仕事を辞める時に「離職」や「退職」という言葉を使いますが、この2つに違いはあるのでしょうか。
次の会社を見つけるために書く履歴書では、どちらを使えばいいのか迷いますよね。
さらに「辞職・退社・休職・転職」との違い、使い方も気になります。
今回は「離職」と「退職」の違いから使い方、さらに「辞職・退社・休職・転職」との違い、使い方についてもご紹介します。
最後に「離職」でイメージする離職率の高い業種についてもふれています。
使い方とあわせてご覧ください!



では早速「離職」と「退職」の違いについて解説します。
離職とは、何らかの理由で職業から離れた状態をいいます。
特に、ハローワークや会社の人事、人材派遣会社などの職員間で使われる言い回しです。
具体的な使い方は、
などが考えられます。
退職とは、勤めている職を退くこと、仕事を辞めることをいいます。
退職金や定年退職、退職届、退職願など、勤めていた会社に関係する事柄で使われることが多いです。
具体的な使い方は
などが考えられます。
「離職」も「退職」も仕事を辞めた時に使われますが、じつは微妙な違いがあります。
それは、離職は仕事を辞めた状態のこと、退職は仕事を辞める行為のことを意味します。
例えば、離職票は「現在職についていない状態」を証明する書類であるのに対して、退職証明書は「この会社を辞めたこと」を証明する書類をいいます。
前述した違いを理解した上で考えると、それぞれ書類の意味合いがよくわかるでしょう。
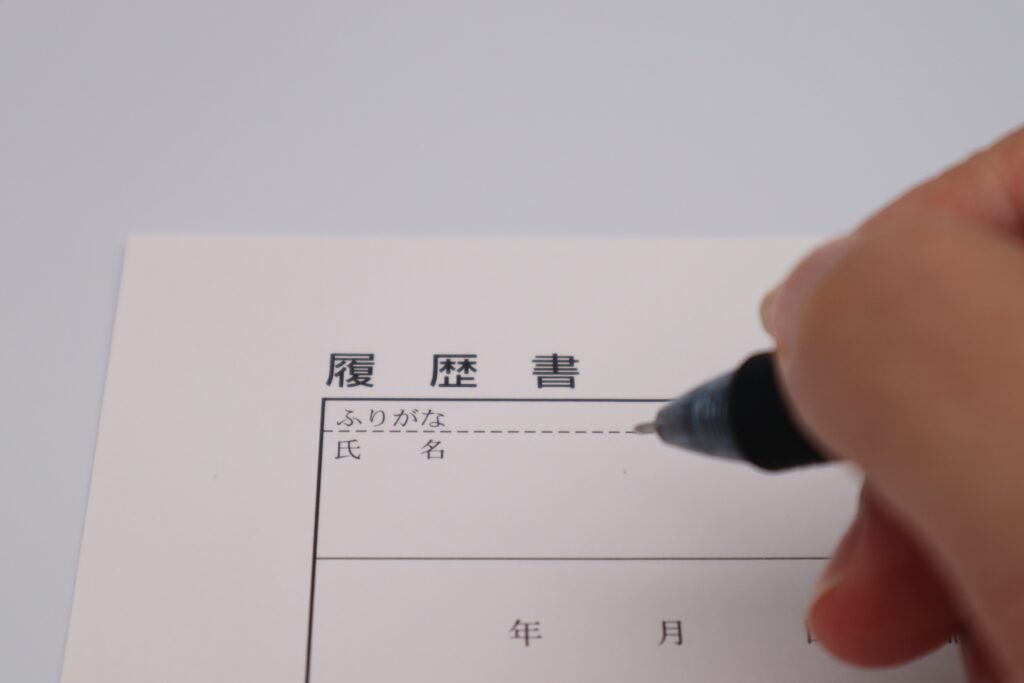
では、「離職」と「退職」は履歴書でどちらを使えばいいのでしょうか。
結論からいうと、履歴書で使う場合は「離職」ではなく「退職」を使うようにしましょう。
だいたいの履歴書には職歴を書く欄があり、そこで「退職」という言葉を使います。
例えば
2020年 4月 株式会社〇〇 入社
2023年 3月 株式会社〇〇 一身上の都合で退職
のような形です。
「一身上の都合で離職」という使い方は一般的ではないので、注意しましょう。
また、履歴書の志望動機や自己PR欄でも退職という言葉を使うほうが無難です。
ちなみに、入社と語尾を合わせて「退社」を使おうと思う人もいるかもしれません。
退社を使っても間違いではありませんが、退職のほうが一般的なので迷ったら退職と記すようにしましょう。なお「退社」の詳しい意味は後述します。

ここまでで、離職と退職の違いがわかったと思います。
しかし、離職や退職と似た言葉は他にもたくさんありますよね…
ここからは、離職、退職と「辞職・退社・休職・転職」など他の言葉との違い、さらに使い方を解説します!
「辞職」とは、就いていた職を辞めることをいいます。退職とほぼ同じ意味をもちます。
しかし、退職は解雇など自らの意思に反して辞めることも含む一方で、辞職は自らの意思で辞める場合しか言いません。
つまり、辞職は自ら職を辞めることを強調した言い方なのです。
使い方としては「全ての責任を取るために辞職します」などが考えられます。
政治家が何らかのトラブルを起こし辞める時も、辞職という言葉がよく使われます。
辞職という言葉を使うことで、周囲から辞めろと言われた訳ではなく、自分の意思で進退を決めたことが強調されます。
「退社」とは、会社から帰ること、会社を辞めること、という2つの意味があります。後者は退職と同じ意味です。
例文は、
などです。
1だとAさんは今日の17時に会社から自宅に帰ったという意味を持ちますが、2だとBさんは3月末付けで会社を辞めたという意味になります。
誤解をうみやすいため、会社を辞めた場合は「退職」、会社から帰った場合は「退社」と使い分けたほうが良いでしょう。
「休職」とは、仕事を休んでいる状態をいいます。こちらは「離職」とニュアンスが似ていますが、全く違う意味を持ちます。
休職の意味を詳しく説明すると、会社との雇用契約を維持したまま、仕事を休んでいる状態をさします。
一方で、離職は会社との雇用契約を終了し、職業から離れています。
休職は解除したら元の会社にすぐ戻れますが、離職は元の会社に戻るならもう一度契約を結ぶ必要があり、手間がかかります。
もし会社に戻る可能性が高いなら、すぐに辞めずに休職するほうが良いでしょう。
「転職」とは、今の仕事を辞めて新しい仕事を始めることをいいます。
離職や退職と同じで、仕事を辞めるという意味もありますが、次の仕事を始めることも含むので全く違う意味をもちます。
例えば
のように使います。

以上で、仕事に関するさまざまな言葉をご紹介しました。
なかでも働く人の多くが経験したことのある「離職」という言葉から日本の「離職率」が気になる方も多いのではないでしょうか。
最後に、離職率が高い業種の特徴をご紹介します。
厚生労働省が発表した「令和3年上半期雇用動向調査結果の概況」によると、離職率の平均は8.1%です。
離職率は正社員やパート社員など雇用形態によっても異なるため、一概に何%からが高いとは言えません。
また、年代によっても大きく異なります。
例えば、新卒者または高卒者の離職率はそれぞれ31.2%、36.9%と全体平均よりも非常に高いことがわかります。
ただ、業種に関しては異業種と比較することで離職率が高いほうなのか、低いほうなのかを判断できます。
厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概況」で最も離職率が高かったのが、宿泊業・飲食サービス業の25.6%でした。
宿泊業・飲食サービス業といえば、ホテルや旅館関係や飲食店などです。
この調査が発表された時期がちょうど新型コロナ流行期にあったため、この結果である可能性もあります。
しかし、飲食店に関しては以前から離職率が高い業種として知られていました。
離職率の高い業種には、ある特徴があります。
以下でそれぞれを解説しましょう。
まずは給与が少ない点です。
「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、最も離職率の高かった宿泊業・飲食サービス業は産業別正社員の平均年収の中で最も低い277万円でした。
飲食業は特に拘束時間も長く、朝から晩まで働いている人は少なくありません。
それなのに、給料が低いと長く続ける気持ちも減退し、離職に繋がりやすくなるのでしょう。
宿泊業・飲食サービス業以外でも、給与に不満を持って転職を試みる人は多くいます。
社員に離職してほしくない会社は、給与面で社員に還元できるようにしましょう。
休日が少ないという点も離職理由に繋がります。
離職率が最も高い宿泊業・飲食サービス業でもそれが言えますが、その次に離職率が高かった生活関連サービス業・娯楽業も休日が少ない業種です。
上記の職種で働く人には、土日祝日は関係なく、連休も取りにくいところが多いでしょう。
また、ゴールデンウィークやシルバーウィーク、夏休み、年末年始などの多くの人が休日を取るタイミングが書き入れ時である点も休日が少ない理由です。
新型コロナの流行により、リモートワークなどの柔軟な働き方は拡がりました。
しかし、離職率の高い業種はリモートワークなど、柔軟な働き方が困難です。
多様な働き方が広がっているからこそ、通常のその場へ行って働くという業種が特に若い人から倦厭されているのかもしれません。
こちらの記事もおすすめ

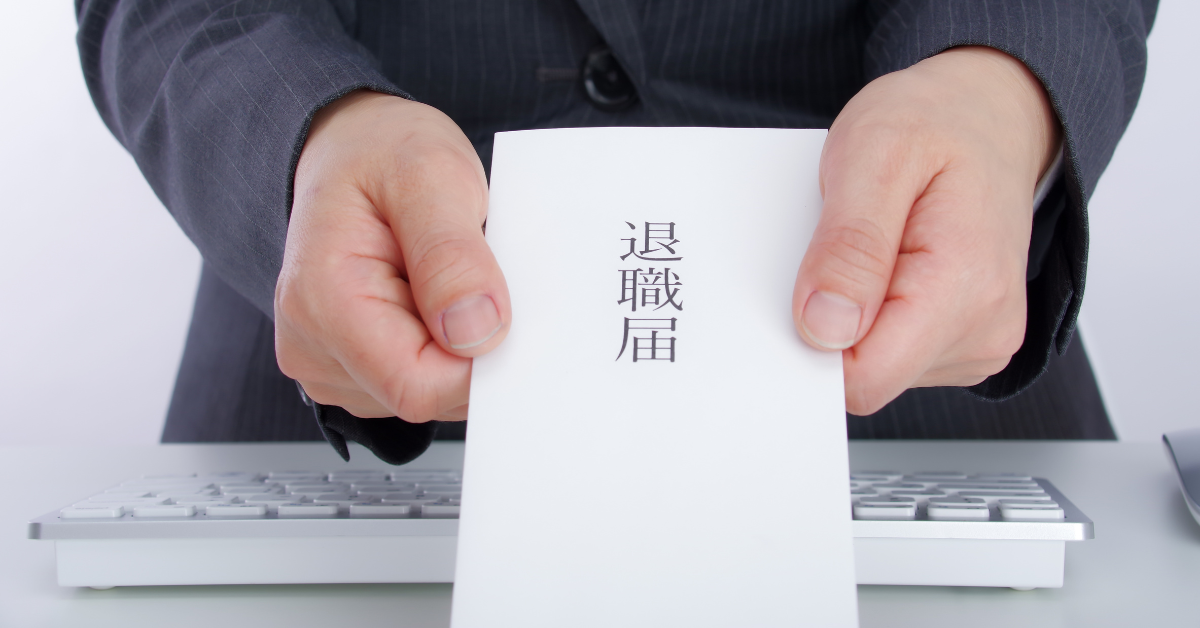

今回は「離職」と「退職」の違いから使い方、さらに「辞職・退社・休職・転職」との違い、使い方についてもご紹介しました。
そして、最後には離職率の高い業種の特徴についてふれました。
「離職」は職業を離れた状態のこと、「退職」は仕事を辞める行為のことを意味します。
微妙な違いなので、使い方には気をつけましょう。
「辞職・退社・休職・転職」も似た言葉ですが、それぞれ意味は違います。
使う時に混同させないように注意が必要です!
この記事を見て、意味や使い方をぜひ参考にしてくださいね。
当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!
審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
当社のおすすめ新着物件はこちら!


