(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)

生活保護には「加算」と呼ばれる、その人の状況によって支給される項目があります。
その加算にもいくつか種類があり、加算額もそれぞれ異なります。
何となく聞いたことがあっても、どんな種類があるのか、いくらもらえるのかなど、難しくてわからない…そんな人も少なくはないはずです。
今回は生活保護の「加算」について、1つ1つわかりやすくご紹介します!
加算額も合わせて紹介するため、生活保護受給者の方や受給を検討している方はぜひ参考にしてください。



まずは、生活保護の加算について簡単に説明しましょう。
生活保護の加算とは、受給者の状況によって支給される手当のようなものです。
加算の種類は、以下の8つです。
それぞれ地域や該当する項目によって、加算額が異なります。
生活保護は住んでいる地域によって、「1級地-1」「1級地-2」「2級地-1」「2級地-2」「3級地-1」「3級地-2」の6区分に分けられます。
都市部と地方では、賃貸物件の相場や食費などの物価が違うため、級地に分けて支給されます。
当然、級地が上がるほど支給額が大きくなるのです。
加算額も地域の等級によって、金額が違うため、ご自身の住んでいる地域の等級を知ることができれば、これからご紹介する加算額の計算が容易になります!
ぜひ、以下のサイトの区分表を見てご自身の地域の等級を知っておきましょう!
https://best-selection.co.jp/media/wp-content/uploads/2021/03/seikatsuhogo-kyuchi2022.pdf
ちなみに、生活保護には、冬の期間中に支給される「冬季加算」という項目があります。
「冬季加算」は「加算」と名前がついていますが、上記8つの加算とは違う種類に分類される生活扶助の1つです。
生活保護には、加算の他にも扶助と呼ばれる支援があります。
扶助には、以下の8項目があります。
加算と似ているため、どう違うのかわからない方もいると思います。
この2つの違いは、扶助は使い道が決まっていますが、加算は自由に使ってもいいという点です。
例えば、医療扶助は医療のみでしか使用できません。また、住宅扶助も同じく家賃分の金額しか支給されません。
一方、加算は決められた金額が支給され、それをどう使用しても自由です。
扶助は実費支給、加算は生活費の一部という扱われ方になります。

さて、ここからは生活保護の加算と加算額について、わかりやすくご紹介します。
ご自身に当てはまる加算をぜひチェックしてみてください!
1つ目は、妊産婦加算です。
妊産婦加算は、妊娠中と産後6ヶ月までの生活保護受給者を対象にしている加算です。
妊娠中と産後は栄養が人一倍必要となるため、加算項目に含まれています。
妊産婦加算額は以下の通りです。
| 級地 | 妊娠6ヶ月未満 | 妊娠6ヶ月以上 | 産後6ヶ月まで |
| 1級地及び2級地 | 9,130円 | 13,790円 | 8,480円 |
| 3級地 | 7,760円 | 11,720円 | 7,210円 |
例えば、1級地に住む受給女性が妊娠6ヶ月以上から出産までもらえる金額が月々13,790円、産後から6ヶ月までもらえる金額が月々8,480円ということです。
2つ目は、母子加算です。
母子加算は、ひとり親の生活保護受給世帯を対象としている加算です。
名称は母子加算ですが、父子家庭も対象となっています。
母子加算額は以下の通りです。
| 1級地 | 母子加算の金額 |
| 児童1名の場合 | 18,800円 |
| 児童2名の場合 | 23,600円 |
| 児童3名以上1名ごと | 2,900円 |
| 2級地 | 母子加算の金額 |
| 児童1名の場合 | 17,400円 |
| 児童2名の場合 | 21,800円 |
| 児童3名以上1名ごと | 2,700円 |
| 3級地 | 母子加算の金額 |
| 児童1名の場合 | 16,100円 |
| 児童2名の場合 | 20,200円 |
| 児童3名以上1名ごと | 2,500円 |
例えば、1級地に住む児童3人がいる世帯の場合、23,600円プラス2,900円で月々26,500円、児童4人がいる世帯は月々29,400円です。
3つ目は、児童養育加算です。
児童養育加算は、18歳未満(高校を卒業する3月末まで)の児童がいる生活保護受給世帯を対象としている加算です。
こちらは地域等級に関わらず、全国一律で児童1人につき、月々10,190円が支給されます。

4つ目は、障害者加算です。
障害者加算は、特定の条件を満たした障害のある生活保護受給者を対象としている加算です。
特定の条件とは以下のどちらかを満たした人のことをいいます。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
わかりやすくいうと、1が身体障害者手帳1級と2級に当てはまる人、または障害年金1級に該当する人、2が身体障害者手帳3級に当てはまる人、または障害年金2級に該当する人のことです。
このあたりは少し複雑です。
例えば、精神障害者保健福祉手帳3級の人はそれだけでは障害者加算の対象にはなりませんが、障害年金を請求し、障害年金2級の支給が決定した場合、障害者加算の対象となります。
ご自身に障害があり、支給対象になり得るのかわからない場合は、担当のケースワーカーに相談してみると良いでしょう。
障害者加算額は以下の通りです。
| 地域の等級 | 該当の条件 | 障害者加算の金額 |
| 1級地 | アに該当する場合 | 26,810円 |
| 1級地 | イに該当する場合 | 17,870円 |
| 2級地 | アに該当する場合 | 24,940円 |
| 2級地 | イに該当する場合 | 16,620円 |
| 3級地 | アに該当する場合 | 23,060円 |
| 3級地 | イに該当する場合 | 15,380円 |
例えば、1級地に住む身体障害者手帳1級の受給者は、月々26,810円が支給されます。
5つ目は、放射線障害者加算です。
放射線障害者加算は、障害者加算とは別に、放射線が原因で障害がある受給者を対象としている加算です。
(1) ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の認定を受けた者であつて、同項の認定に係る負傷又は疾病の状態にあるもの(同法第24条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者に限る。)
イ 放射線(広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の放射線を除く。以下(2)において同じ。)を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であつて、当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの
(2) ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた者(同法第25条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者であつて、(1)のアに該当しないものに限る。)
イ 放射線を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であつた者であつて、当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
| 該当する条件 | 放射線障害者加算金額 |
| (1)に該当する者 | 44,620円 |
| (2)に該当する者 | 22,310円 |

6つ目は、介護施設入所者加算です。
介護施設入所者加算は、介護施設に入所している生活保護受給者を対象としている加算です。
なお、母子加算、障害者加算が支給されている人は対象外となります。
施設内での理容や美容品、嗜好品、教養娯楽品などの購入を想定して支給されます。
介護施設入所者加算額は、全国一律で月々9,880円です。
7つ目は、介護保険料加算です。
介護保険料加算は、介護保険の第1号被保険者、つまり65歳以上の生活保護受給者を対象としている加算です。
一般的には65歳以上の人も介護保険料を支払う必要があります。しかし、生活保護受給者は納付すべき介護保険料に相当する金額をこの加算で補うことができます。
つまり、支払うべき介護保険料を実費負担してくれるのが介護保険料加算ということです。
最後8つ目は、在宅患者加算です。
在宅患者加算は、在宅で療養している生活保護受給者を対象としている加算です。
療養のために必要となる栄養補給などを目的として支給されます。
在宅患者加算額は、1級地及び2級地で月々13,270円、3級地で月々11,280円です。
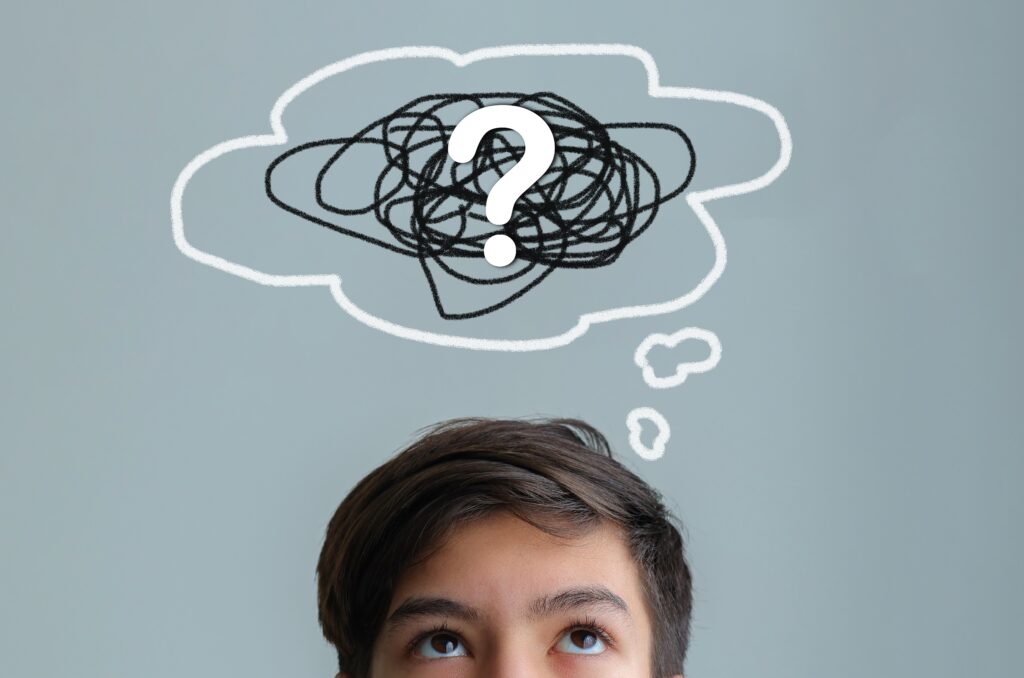
生活保護の基本的な加算は上記の8つです。
しかし、2023年から特例加算と呼ばれるものが施行され、さらに2025年4月からその特例加算が増額されたことで注目を集めました。
最後に、生活保護の特例加算についてご紹介します。
生活保護の特例加算は、生活保護費の見直しの際に施行されました。
当初の予定は2023年度から2025年度までの2年間限定で、生活保護の世帯員1人に対して月額1,000円を一律で上乗せする内容でした。
しかし、新たな検討により2025年度より、この月額1,000円に対して500円が追加された月額1,500円の加算が発表されたのです。
現時点で月額1,500円の加算は、2025年度から2年間と決まっています。
この特例加算の支給理由は、近年の物価高への対応です。
日本の物価高が顕著となったのは2021年の後半からと言われており、世界インフレの影響を受けたためです。
2025年に入ってからは、特に食料品の高騰が進んでおり、日本人の主食であるお米に関しては前年度に比べて90%以上値上がりしています。
つまり、約2倍の金額です。
一般家庭で家計が圧迫されるのは当然ですが、生活保護受給者にとっては更なる節約が強いられます。
夏になると、エアコン料金も追加されるため、命に関わる深刻さとなるでしょう。
世帯員1人につき月額1,500円の加算だけでは、この物価高を乗り切れないという声も少なくはありません。
特に、高騰した食費などに加え、前述した夏のエアコン料金を支払えない受給者は少なくないでしょう。
そのため、生活保護受給者への夏季加算を新たに加算するようにという声も高まっています。
生活保護の特例加算などについて、今後も変更される可能性があります。
引き続き、注目を続けます。
こちらの記事もおすすめ



今回は生活保護の「加算」について、1つ1つわかりやすく、金額も合わせてご紹介しました。
加算とはその人の状況に合わせて支給される手当のことです。
この記事を読んで、自分にはどのような加算が当てはまって、いくら支給されるのか、把握できたでしょうか?
加算をつけ忘れてもらえていなかった、なんてこともあるようなので、自ら情報を集めておくことが大切です。
(加算額は厚生労働省「○生活保護法による保護の基準」より引用:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0)
当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!
審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
当社のおすすめ新着物件はこちら!


