(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)

生活保護を申請または受給すると、必ず家庭訪問を受けることになります。
生活保護受給を検討する人は、この家庭訪問がどのような内容で何を見られるのか、非常に気になりますよね。
今回は生活保護の家庭訪問はどんな感じ?初回から定期訪問まで、何を見るのかを徹底解説します。



まず、生活保護の家庭訪問を行う目的について解説しましょう。
生活保護の家庭訪問は、申請者や受給者の生活状況を把握するために行われます。
書面上で生活が苦しいと訴えても、実際の生活状況では本当かどうか判断がつきません。
しかし、自宅を見るとある程度、生活状況が把握できます。
例えば、どのような部屋に住んでいるのか、どのような家具や家電を使用しているのか、宝石のような高価な物品を大量に保有していないか、などです。
もし高価な物品を大量に保有している場合、家庭訪問で売却するように指導を受ける可能性があります。
ただし、それらの基準は自治体やケースワーカーによって異なります。
不明な点は、担当のケースワーカーに尋ねるようにしましょう。
生活保護の目的は受給者の生活を自立させることです。
生活保護費を支給するだけで、受給者がどのような生活を送っているのか確認しなければ自立支援にはなりません。
そのため、家庭訪問を行い、日常生活に困り事がないか、就職活動はどのように行っているかなどをチェックします。
電話などでも受給者の状態は確認できるのでは?と思う人もいるかもしれませんが、家庭訪問に大きな意味があります。
たとえ外で調子が良さそうに見えても、自宅ではゴミだらけで生活が荒れている場合もあるでしょう。適切な食事を摂っていない、または家族に摂らせていない可能性も考えられます。
そういった状況を防ぐために、家庭訪問は生活保護にとって大切な事柄なのです。
度々ニュースなどで問題になる生活保護の不正受給も家庭訪問によって防止できます。
不正受給のほとんどは悪意のない、受給者の知識不足によるものが多いです。
しかし、一部では働いていることを隠して、生活保護費を受給する悪質なものもあります。
そういった悪質な不正受給はバレないと思ってやっていることが多いでしょう。
ケースワーカーが度々家庭訪問で訪れていると、不正受給するとバレる可能性が高いと感じさせることができます。それは、悪いことを考える人にとって大きな予防に繋がるでしょう。
多くの経験を持つケースワーカーにとって不正受給者の怪しい行為はすぐにわかるものです。不正受給をするのは絶対にやめましょうね!
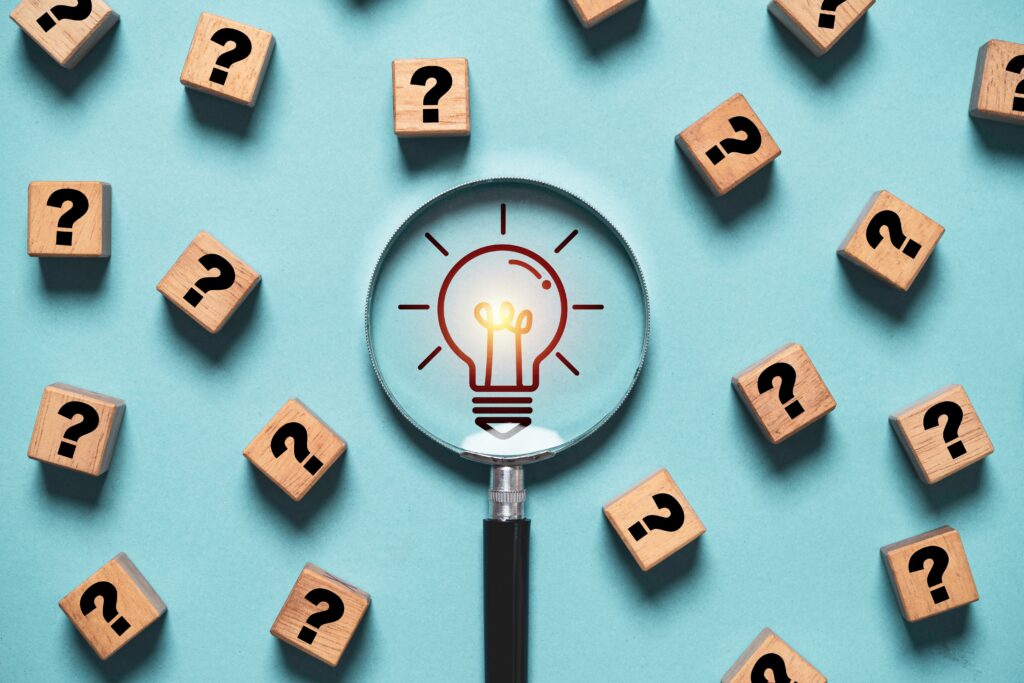
家庭訪問の目的は生活状況の把握や自立支援、不正受給を防止するためとさまざまですが、具体的にはどのような部分を見るのでしょうか。
さらに、生活保護の家庭訪問には「初回家庭訪問」と「定期家庭訪問」「臨時家庭訪問」があり、それぞれに見る部分が異なります。
ここからは、生活保護の家庭訪問で何を見るのかを家庭訪問の種類別で解説します。
生活保護を申請すると、審査中の間に初回の家庭訪問を実施します。
初回家庭訪問では、申請内容に誤りがないかを簡単に確認します。
大きなテレビなど豪華な家電があった場合、いつ頃購入したのかなど聞かれる可能性があります。
しかし、一般家庭に普及率70%以上の家電は生活必需品と見なされ、保有が認められています。
あまりにも高価なもの以外は、売却するように指導されることはないでしょう。
安心して初回家庭訪問を終わらせましょう。
生活保護の受給が開始したら、定期的に家庭訪問が行われます。
定期家庭訪問では、生活状況や自立に向けた生活を送れているかを確認します。
例えば、部屋が汚れていて健康を害する可能性はないか、服薬が正しく行われているか、などです。
また、初回家庭訪問でなかった新たな家具・家電が増えている場合、生活保護費でどのようにして購入したのかを尋ねられることもあるでしょう。
コツコツ保護費を貯めて購入したのであれば、問題になる可能性は低いです。
ケースワーカーも担当世帯数が多いため、簡単な質問だけ行い、数十分で帰る場合がほとんどです。
安心して正直に答えるようにしましょう。逆に、変な反応をすると怪しまれる可能性もあるので注意が必要です。
生活保護の家庭訪問は、定期的なものだけでなく、臨時で行われるものもあります。
例えば、病院から退院したばかりで健康状態に不安がある、就職が決まりそうな状態にあるなどの場合です。
偶然近くに寄ったから、ついでに家庭訪問する場合も考えられます。
上記のようなケースだと、健康や仕事に関する簡単な質問で家庭訪問は終わります。
また、不正受給が疑われている場合や指導を全く聞かない場合も同様に、複数回にわたる臨時家庭訪問が行われます。
その場合、ケースワーカーは厳しい質問や家庭訪問を入念に行うことになるでしょう。

では、一般的な生活保護の家庭訪問の頻度はどのくらいなのでしょうか。
厚生労働省によると、生活保護のケースワーカーによる家庭訪問は1年に2回以上行うように定められています。
つまり、一般的には3〜6ヶ月に1回程度です。
しかし、前述した通り、受給者の状況によって頻度は異なります。
ケースワーカーは受給者の状況に応じて訪問頻度をランク付けしています。
例えば、ケースワーカーの指導を聞いて真面目に自立を目指す受給者は家庭訪問の頻度が少なく、指導をあまり聞かない受給者であれば家庭訪問の頻度は多く設定します。
しかし、家庭訪問が多いからといって不真面目と思われている訳ではありません。
前述してきた通り、退院してすぐ、または健康状態が優れないなど特に支援が必要な受給者や、就職が決まりそうな受給者など、特別な理由があると家庭訪問の頻度は高くなります。

では、最後に生活保護の家庭訪問を受ける際の注意点をご紹介しましょう。
生活保護を検討中の方から受給したばかりの方まで、ぜひ参考にしてください!
生活保護の家庭訪問は拒否できません。
生活の実態が把握できないと、生活保護費は支給できないため、当然です。
ただし、ケースワーカーによっては、部屋の中を簡単に確認するだけで、その後の話は玄関先で行ってくれる場合もあります。
特に、女性受給者で男性ケースワーカーが部屋に長く滞在することに抵抗がある人は、一度相談しても良いかもしれません。
理由もなく家庭訪問を拒否すると、不正受給などを疑われる原因となるため、注意が必要です。
生活保護の家庭訪問は、アポありの場合とアポなしの場合があります。
特に、仕事をしていない受給者は在宅が多いと思われるため、アポなしで訪問される可能性も高いです。
また、ケースワーカーのやり方によってアポとりをする人としない人で別れるようです。
アポなし訪問の場合、不在が多いと、隠れてどこかで働いているのか、友人などに援助してもらっているのか、などと怪しまれかねません。
不正なことをしていないのに疑われるのは嫌ですよね。
もし不在時にケースワーカーが来ていた場合、メモが残されていることが多いため、すぐにケースワーカーへ連絡を取り、家庭訪問の約束を行うようにします。
そうすることで、不在の数が減り、怪しまれる可能性が低くなるでしょう。
生活保護の家庭訪問は、受給者1人とケースワーカー1人のやり取りが密室で行われる場合が多いです。
そのため、ケースワーカーから不適切な発言や指導が入る可能性もあります。
もし、そのようなことがあれば、住んでいる自治体の福祉オンブズマン(オンブズパーソン)制度を利用しましょう。
福祉オンブズマンとは、福祉サービスを利用する人の苦情を第三者機関として公正かつ中立の立場で調査する制度をいいます。
調査だけでなく、解決のために動いてくれるため、安心して相談しましょう。
ただし、ケースワーカーは生活保護受給者へ生活指導や家計指導、自立に向けた指導を行う務めがあります。
受給者が不適切な指導と感じても、実際は必要な指導の可能性も多いため、一度冷静になって考える必要があるでしょう。
こちらの記事もおすすめ



今回は生活保護の家庭訪問はどんな感じ?初回から定期訪問まで、何を見るのかを徹底解説しました。
生活保護の家庭訪問は、申請者または受給者の生活状況を知るため、自立を支援するため、不正受給を予防するためなどの理由で行われます。
初回家庭訪問では、申請内容に誤りがないか生活状況を確認します。
定期家庭訪問では、生活状況と一緒に自立に向けた生活が行われているかを確認します。
臨時家庭訪問では、健康や仕事の状況、不正受給を疑って行う場合があります。
ケースワーカーによって異なりますが、怪しい点がなければ、部屋の隅々まで確認されることは少ないでしょう。
家庭訪問は拒否できないため、素直に受け、不在が多くならないように注意します。
ただし、ケースワーカーから不適切な指導があった場合はオンブズマン制度を利用し、苦情を行うようにしましょう。
当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!
審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
当社のおすすめ新着物件はこちら!


