(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)

「生活保護でも貯金はいくらまでできる?」
「そもそも貯金できるの?」
と悩んでいませんか?
生活保護を受けていると貯金ができないイメージを持つ人もいますが、実はできます!
しかし、ポイントを押さえて計画的に行うことが大事です。
今回は、生活保護でも貯金するために必要な情報をまとめました!
生活保護を受けている人も、受給を検討している人もぜひ参考にしてください。



生活保護を受けている人の多くは、将来に備えていくらかの貯金をしたいと思いますよね。
実は、生活保護受給者でも貯金をすること自体は可能です。
最初にその事実を確認しておきましょう!
生活保護を受ける人の中には、「貯金があってはいけない」と誤解している方も多いですが、実際には貯金の上限が法律で決められているわけではありません。
しかし、貯金の金額や方法によっては、生活保護の受給に影響を及ぼす可能性があります。
生活保護受給中に貯金するポイントについては、後ほど詳しくお伝えします。
先ほど、生活保護受給中でも貯金するのは問題ないとお伝えしましたが、取り扱いについては自治体によって若干の違いがあります。
一部の自治体では、生活保護受給者の貯金額に対して一定の基準を設けている場合もあります。
そのため、貯金をしたい場合は自分が居住する自治体での詳しい規定や手続きを確認しておくのがおすすめです。
また、必要に応じてケースワーカーに相談しましょう。
自治体によっては制限される場合はあるものの、上限なく貯金できる条件があります。
たとえば、以下のような条件の場合は、貯金の上限はありません。
・自立のための資金
・子供の学費や進学費用
・親の介護費用
また、自立や就職に必要とされる場合は、免許取得や引っ越しなどの資金も上限なく貯金できるといわれています。
生活保護の基本原則は、受給者が自立し、困難な状況から脱することを助けることにあります。
そのため、自立のための貯金の金額がいくらであっても、問題視されないことが多いのです。

生活保護を受けている人でも貯金できるのは、どんな理由があるのでしょうか。
ポイントを解説します。
生活保護制度の最終目標は、受給者の自立支援にあります。
そのため、以下のような自立に必要な資金の貯金は明確に認められています。
自立のための貯金のポイントは、貯金の目的を明確にし、いつまでに、いくら、なぜ必要なのかをケースワーカーに説明できることです。
生活保護制度では、子どもの教育や未来のための貯金が認められています。
生活保護制度が単なる生活支援だけでなく、受給者とその子どもたちの将来的な自立を支援する理念に基づいているためです。
具体的には、小・中学校や高校、大学の学費、教材費、制服代など、子どもの健全な学校生活に必要な資金の貯蓄が許可されます。
とくに大学進学には多額の費用が必要となるため、子どもの教育を支援する目的での貯金は重要視されています。
将来の不測の事態への対応のために、生活保護費の貯金は認められています。
たとえば、以下のような将来の生活に必要な資金を準備する場合が該当します。
とくに、結婚式の参加費やご祝儀に充てる費用は自己負担となるため、行事に備えて生活保護費から貯金しておく必要があります。

生活保護を受給しながら貯金をする際には、いくつかのポイントを理解しておくことが大切です。
受給中の方で貯金を考えているなら、ぜひチェックしておきましょう!
生活保護を受けているときに、貯金の事実をケースワーカーに隠すべきではありません。
計画的に貯金をしていること、その目的や方法を正直に伝えることが重要です。
たとえば、タンス貯金などで隠れて貯めているのが発覚しますと、信頼関係を損ねる原因となり、場合によっては生活保護自体が停止する可能性もあります。
生活保護受給者が貯金をする場合、望ましいとされるのは自立するための資金として貯めることです。
たとえば、具体的な貯金の目的としては、まず就職活動をスムーズに行うための交通費が考えられます。
面接に足を運ぶための費用や企業訪問に使われるもので、直接的に就業機会の獲得に繋がる重要な支出です。
また、資格取得やスキルアップのための学費も大切です。
教育的投資は、長い目で見たときに職業の選択肢を広げ、安定した収入を得るための基盤を築くために不可欠となっています。
最終的に生活保護から抜け出すためにも、前向きで計画的な貯金が重要であり、社会的な自立を促す手助けとなります。
貯金がある程度以上の高額になると、生活保護の受給資格を失う可能性があります。
なぜなら、生活保護の基準を上回るだけの資産があると判断されるためです。
生活保護は本来、最低限度の生活を維持するための制度であり、貯金がその基準を超えると、自立可能な資産を持っているとみなされる可能性が高まります。
とくに貯金額が増加している場合は、将来的な生活保護の受給に関する計画を立てることが重要です。
たとえば、自分の資産状況を定期的に見直し、万が一に備えてケースワーカーに相談することが推奨されます。
ケースワーカーは、生活保護受給者の貯金を含めた全体的な経済状況を確認し、適切なアドバイスを提供します。
また、自分の資産が不明確な場合は、まずは正確な資産管理を行い、どの程度の貯金を持っているのかを把握することが大切です。
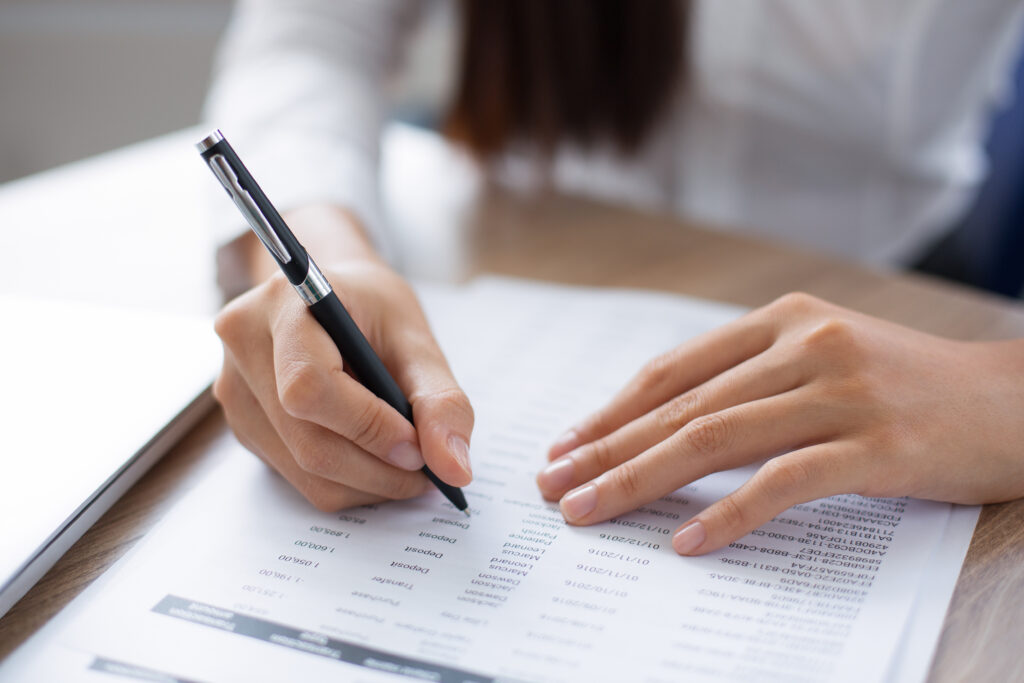
貯金がある場合でも、その金額で生活が困難であれば生活保護の申請が可能です。
具体的には、貯金の金額が国が定める最低生活費以下であれば受給できます。
重要なのは、申請する際にすべての財産情報を正確に申告することです。
貯金があるからといって、必ずしも生活保護の受給が難しくなるわけではありませんが、金額によっては生活保護の受給額が調整されるので注意しましょう。

生活保護は、必要な人にだけその支援が行き渡るように、申請者の財産状況は厳しくチェックされます。
とくに、貯金の額はその人の経済状態を判断する重要な基準の1つなので、申請時だけでなく受給中も随時調査が行われることがあります。
最後に、どのようなタイミングで貯金が調査されるのか、確認しておきましょう。
生活保護を申請する際に行われるのが、貯金を含む資産状況の調査です。
この時点で、貯金があっても生活保護の申請ができるのかがチェックされます。
申請が通る貯金額としては、地域や家族構成、年齢などによって異なり、一概にいくらまでとは言えません。
ただし、貯金額が多すぎると資産があると判断され、生活保護の支援は受けられないので注意しましょう。
生活保護の受給が開始された後にも、定期的に自己の資産状況を申告する必要があります。
少なくとも年に1度、資産申告書を提出し、貯金や現金、不動産など、どれくらい持っているのかを申告することによって、引き続き生活保護の支援が必要かどうかが評価されます。
もし、申告せずに資産が増えたことが後から発覚した場合、生活保護の不正受給とみなされることがありえます。
そのため、貯金が増えたとしても正確な情報を申請するようにしましょう。
生活保護制度では、ケースワーカーが受給者の生活状況を定期的に訪問します。
この訪問が行われる理由の1つが、受給者の経済状況に変化がないかを確認することです。
もしブランドものを身につけるようになったり、生活水準が上がっていたりなど不審な点があった場合、ケースワーカーは貯金の状況について詳しく調べることがあります。
その際、貯金に関する情報が不透明であると、生活保護の受給資格に影響を及ぼすことも考えられます。
生活保護を受けていても、貯金することは可能です!
ただし、貯金の目的は自立のためであることがポイントです。
また、隠れて貯金したり、資金と判断される額を貯め込んだりすると生活保護の受給が打ち切られる可能性があります。
貯金は計画的かつ、管理しながら行ってみてくださいね!
当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!
審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
生活保護受給者向けのおすすめ新着物件はこちら!


