(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)
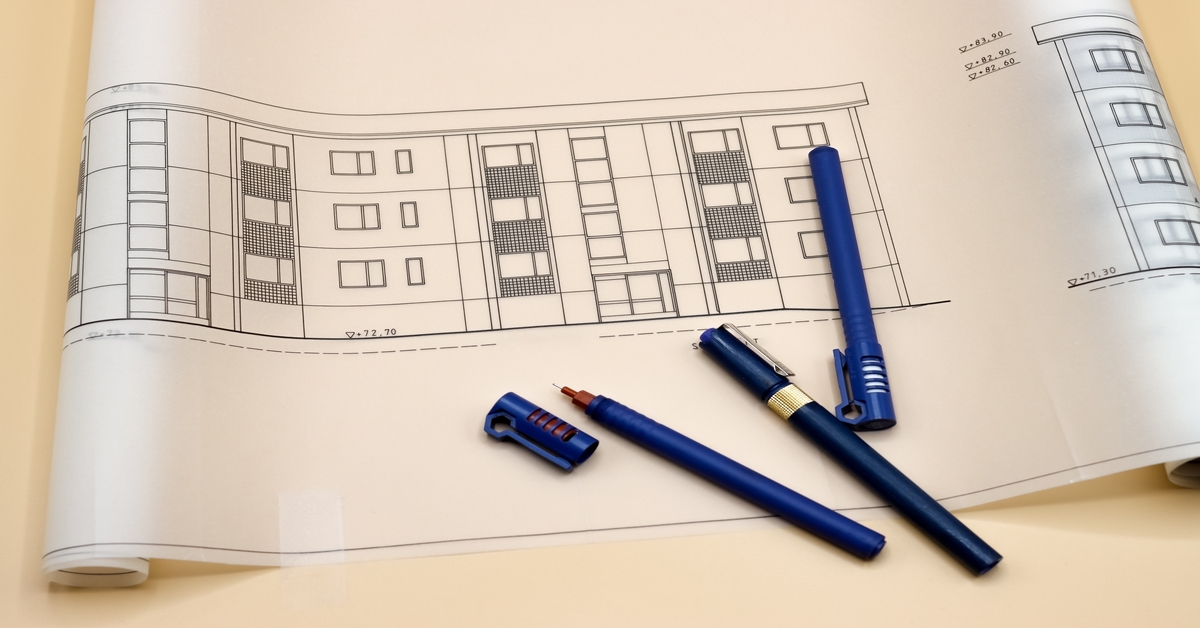
生活保護受給者は住宅扶助を受け取れるため、安心して部屋に住み続けることができます。
この時、多くの人が気になるのが生活保護受給者が住める部屋の広さは決まっているのかについてです。
結論から言いますと、部屋の広さに上限はありませんが、単身世帯に限っては部屋の広さに応じて住宅扶助が変動します。
本記事では、生活保護受給者が住める部屋の広さを中心に解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。



生活保護受給者が住める部屋の広さは特に定められていません。
しかし、最近になり、部屋の広さに関するルールが作られ、単身世帯に限り適用されています。
ここからは部屋の広さに関する話題を解説します。
結論から言いますと、部屋の広さは原則自由です。
例えば、法律において部屋の広さに上限を定めると、全国各地で適用されるため、結果として住宅扶助の金額が大きくバラつく可能性があります。
茨城県では25,000円の家賃で間取り2Kの家があるなど、家賃が安くても広い部屋に住めるケースもあります。
生活保護受給者は必要以上に広い家に住んではいけないなどのルールはないのです。
生活保護受給者に与えられたルールは、「住宅扶助で家賃などの支払いができればいい」というルールです。
住宅扶助内で家賃などが賄えるのであれば、原則どの家に住んでも問題はありません。
そのため、生活保護受給者は住宅扶助の金額をメインに、家探しを行っていきます。
一方で、住宅扶助には例外があります。
単身世帯に関しては部屋の広さに応じて住宅扶助が変動するのです。
平成27年から住宅扶助の見直しが行われ、世帯人数によっては減額や増額がなされています。
東京都23区の場合、2~6人世帯は69,800円が住宅扶助の金額でしたが、2人世帯は64,000円に減額された一方、6人世帯は75,000円に増額されました。
一方、単身世帯は原則変動なしとされましたが、床面積別に上限が設定されたのです。
同じ単身世帯でありながら、床面積の違いだけで最大2万円近い違いが生じています。参照:東京都
部屋の広さは決まっていないものの、床面積の違いでこれだけの差が生じるのです。
2013年から2015年にかけて住宅扶助は引き下げられ、引越しを余儀なくされた生活保護受給世帯は44万世帯もいました。
実は引き下げの前段階で、生活保護受給者が住む家に関して、最低居住面積水準をクリアしたケースが少ないことが指摘されていました。
一般世帯において、単身世帯だと76%、複数人の世帯では86%の達成率だったのに対し、生活保護受給者の場合は単身世帯で46%と半数を割り込み、複数人の世帯でも67%と低い達成率でした。参照:全国青年司法書士協議会
引き下げの根拠として、一般世帯の家賃より生活保護受給者の家賃の方が高い傾向にあることが挙げられていましたが、実態としてはそう言い切れない面があります。

部屋の広さはどうでもいいと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、国土交通省では、住生活基本計画における居住面積水準を定めており、「健康で文化的な住生活の基本とし必要不可欠な住宅面積に関する水準」として最低居住面積水準を定めています。参照:国土交通省
ここからは最低限必要な部屋の広さについてまとめました。
国土交通省が定める最低限必要な部屋の広さは、単身世帯では25㎡としています。
明確な基準があり、就寝・学習に5㎡、食事・団らんに2.5㎡、排泄に1.8㎡など機能スペースが定められています。
加えて動線空間も別途確保され、最終的に25㎡という数字が出ている状態です。
ちなみに2人の居住で30㎡、3人で40㎡と定められており、この面積を確保することで、「健康で文化的な住生活の基本として必要不可欠な住宅」となり得るのです。
東京23区において、25㎡の平均家賃をランキングにまとめたサイトがあります。
その中で最も安いのが足立区で68,800円、2位が葛飾区で69,611円、3位が江戸川区で70,338円でした。
ちなみに最も高いのが港区で141,428円とその差は倍以上です。参照:PRTIMES
単身世帯の住宅扶助は25㎡であれば上限の53,700円となりますが、どの区の平均家賃からも大きく下回ることになります。

生活保護受給者が住む部屋の広さが狭いことでどのような影響があるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
本項目では、部屋が狭い影響についてまとめました。
部屋が狭いと、家具などを置くとゆったり過ごせるスペースはかなり狭くなり、圧迫感を感じます。
圧迫感は時に息苦しさを感じ、精神的に悪影響が出る恐れがあります。
一方、広さを少しでも確保しようと家具などをできる限り置かないようにするケースもありますが、むしろ殺風景で寂しく感じる時も出てくるでしょう。
部屋が狭いことで圧迫感がどうしても出てしまい、家具を置く・置かないに関係なく、何かしらの悪影響が出やすくなります。
部屋が狭いことで、収納場所が少なく、収納が確保できないことが考えられます。
収納が少ないと片付けることが難しくなり、部屋が散らかりやすくなるケースが出てくるでしょう。
最近はベッドに収納がついているケースもありますが、生活保護を受け取っている中ではなかなか購入するのは大変です。
無理に収納を確保しようとすると、圧迫感にもつながります。
生活保護を受け取りながら、お子さんと一緒に暮らす方もいるのではないでしょうか。
部屋が狭い場合、子ども1人に十分な空間を与えられず、ストレスを与えてしまうことが考えられます。
特に母親と息子、父親と娘のように性別が異なる親子だと、思春期を迎えるにあたり、相当なストレスが生じることが想定されます。
なるべく部屋数があることが理想的ですが、都心部において探すのは大変です。

生活保護受給者が少しでも広い部屋に住みたい場合にはいくつかの対処法があります。
その対処法をまとめました。
最もおすすめなのが、生活保護受給者向けの物件を中心に広い部屋を探すことです。
25㎡を上回る部屋は多くはないものの、全くないわけではないほか、25㎡に近い物件は探せば十分にあります。
生活保護受給者向けの物件は柔軟な審査などを行うため、審査が通るかどうかを過度に心配しなくて大丈夫です。
床面積の違いでもらえる住宅扶助の金額が違うため、できれば15㎡以上の物件で探すのがおすすめです。
15㎡以上なら53,700円を意識した物件を探せるため、わかりやすいと言えます。
せっかくいい物件であっても、床面積が狭いために断念せざるを得ないケースも出てくるでしょう。
生活保護受給者向けの物件の中には15㎡以上の物件が多く、53,700円という金額で理想的な住居を見つけ出すことが可能です。

生活保護受給者にとっては定住できる部屋を確保することが大切であり、安心できるポイントと言えます。
同時に、一定の部屋の広さがあってようやく最低限度の生活を実感できるとも言えるでしょう。
部屋の広さに妥協せず、ここならば自尊心を損なわずに住めるという物件を見つけていくことをおすすめします。
当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!
審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
当社のおすすめ新着物件はこちら!


